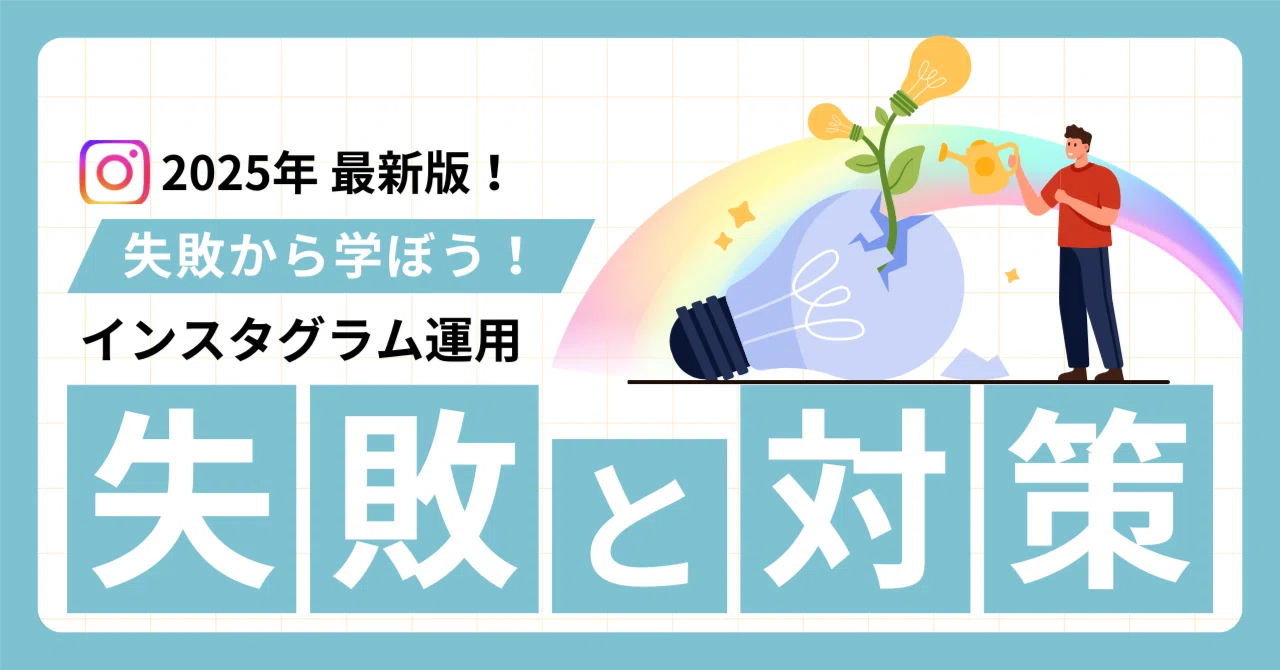いざInstagram運用を始めても、
フォロワーがなかなか思うように増えない、
いいねやコメントが付かず、
伸び悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
実は自己流で闇雲に投稿するだけではフォロワーは増えません。
そこで今回は、インスタグラム運用のよくある失敗事例と対策について
解説していきます。
失敗例①投稿に一貫性がない
「オシャレな投稿をしているのにフォロワーが増えない…」
「毎日投稿しているのに売上に繋がらない…」
と悩んでいる方のアカウントを見ると、
ジャンルがバラバラ、色も雰囲気も統一されていないということが
多いです。
一貫性のない投稿とは、以下のような状況を指します。
- 毎回ジャンルが違う(例:美容→旅行→副業→ペット)
- デザインがバラバラで統一感がない
- 投稿の口調(話し方)が毎回違う
- 個人の日常とビジネスの話が混在している
「誰に何を送っているのか」が不明瞭になっており、
どのような人が運用しているのか、
何の情報を発信しているアカウントなのかが
分からないため、フォローされにくくなっています。
一貫性のない投稿が失敗につながる理由は大きく3つあります。
①世界観が伝わらないため記憶に残らない
インスタグラム内には多くの投稿が溢れており、
投稿を見るか見ないかは一瞬で判断されます。
最初の数秒で「この人の投稿、好きかも!」と感じさせられなければ、
スクロールされてしまいます。
統一感のない投稿だと記憶に残らず、フォローにもつながりません。
②「誰向け」の投稿かわからず、共感が生まれない
特に投稿内容にばらつきがあったり、
ジャンルが固定されていなかったりすると、
「誰向け」の投稿か不明瞭になってしまいます。
人は「自分に向けて発信されている」と感じた時に初めて反応します。
誰にとっても大事な内容は、誰にとっても響かないのです。
③検索に弱くなる
統一感のない投稿は、アルゴリズムにも評価されづらく、
発見タブや検索結果も表示されにくいです。
その結果、リーチが伸びず、運用の成果も出にくくなってしまいます。
特に運用初期のファンが少ない時期には、
一貫性があるコンテンツを継続して
コツコツと投稿していくことが大切です。
何をテーマに発信していくのか、
発信情報の軸をしっかりと決めましょう。
また投稿に一貫性を持たせる方法として、
デザインの統一感は不可欠です。
色、フォント、イラストや写真のテイストを固定し、
アイコン、投稿デザイン、ハイライトデザインなど
アカウントを開いたときに目に入るものは全て統一感を出しましょう。
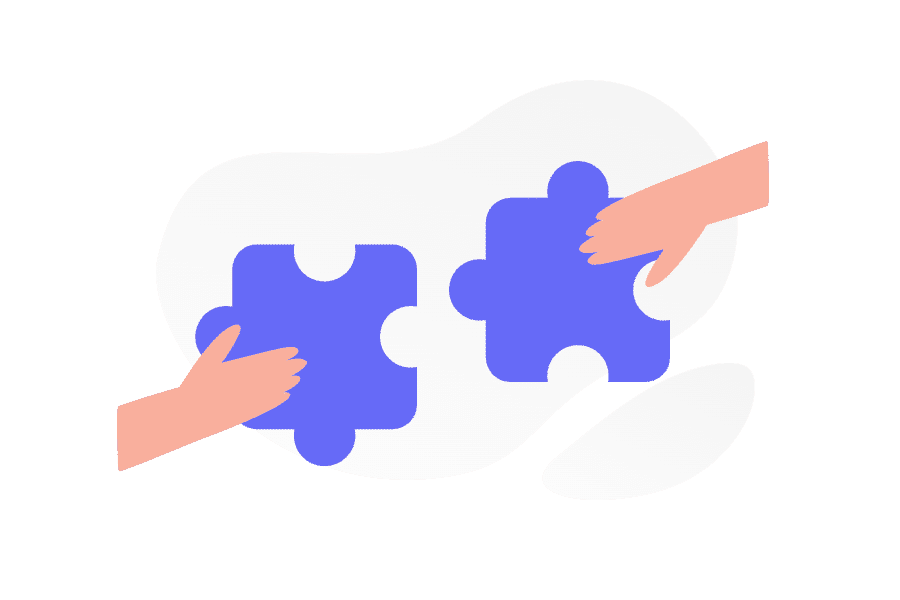
失敗例②フォローバックを目的に闇雲にフォローする
インスタを始めたら、
まずはフォロワー数を増やしたいと考えるものです。
インスタユーザーの中には、
フォローされたら必ずフォローし返すという方もいます。
そのためできるだけ多くのアカウントをフォローすれば、
フォロワー数を増やしていけそうな気がしてしまうかもしれません。
しかし、この方法ではフォロワー数は増えるかもしれませんが、
長期的に見ると失敗につながる恐れがあります。
① エンゲージメントが低い
フォローバックされたとしても、あなたに興味がない人であれば、
投稿を見られることはなく「いいね・保存・コメント」などの
アクションは起きません。
エンゲージメント率が下がると、
インスタのアルゴリズムから「質の低いアカウント」と判断され、
リーチが減少します。
②アカウントの信頼性が低い
フォロワー数よりフォロー数が圧倒的に多いと、
「数だけを追っているアカウントなのかな?」と
不信感を持ってしまうユーザーも多いようです。
③ 質の高いフォロワーが育たない
インスタ運用の目的が「集客」や「信頼構築」であれば、
質の高いフォロワー(=投稿をしっかり読んでくれる人)が必要です。
ただし、フォローバック目的のユーザーは、
商品やサービスに興味を持っていないため、
結果的に「集客ゼロ」という状態に陥ります。
④アカウント凍結のリスク
インスタグラムのポリシー上、過剰なフォロー・アンフォローは
スパム行為とみなされ、短期アカウントのシャドウバンや凍結リスクも
あります。
正確な数値は公表されていませんが、
1日で100件以上のフォローやキャンセルを行う行為は、
アルゴリズムに悪影響を与えるため控えましょう。
▶︎正しいフォロワーの増やし方は「質×共感×導線設計」
ステップ1:価値ある投稿で「自然な共感」を生む
人は「自分にとって価値がある」と感じたときに初めてフォローします。
例えば、下記のような発信は有益情報を感じやすいです。
- ノウハウ提供(例:初心者向けのインスタ解説)
- 共感型のストーリー(例:ビジネスで挫折した経験談)
- Before/After事例(例:運用前→運用後の改善結果)
投稿自体が「フォローする理由」になっていることが重要です。
ステップ2:プロフィールで「誰の・何のアカウントか」を明確にする
どれだけ良い投稿でも、
プロフィールが簡素すぎるとフォローにはつながりません。
- 何者か、誰に何を提供しているかが明確か?
- 特典・プレゼントなど、フォローする特典があるか?
- 他のSNSやLINEへの導線があるか?
プロフィール文の改善だけで、フォロワーが増えたケースは多くあります。
ステップ3:リール・ストーリーを活用して拡散&信頼構築
リールは非フォロワーに届く唯一の機能です。
ここで「認知」を獲得し、
ストーリーや投稿で「信頼」を獲得しましょう。
- リールで拡散→プロフィールへ誘導
- ストーリーで発信する人柄や裏話見せて信頼を構築
- フィード投稿で専門性・価値提供を行う
このように段階的な導線を設計することで、
フォロワー増加につながります。
失敗例③ユーザーにとって必要な情報が書かれていない
フォローやエンゲージメントにつながらない投稿で悩んでいる場合、
ユーザーにとって必要な情報が抜けている場合があります。
具体的には以下のような投稿が該当します。
- 専門用語や抽象表現が多く、初心者には伝わらない
- やり方、方法が抜けていて実践できない
- 商品・サービス紹介で「価格・申し込み方法」が書かれていない
- 場所や日程、期間など「行動に必要な情報」がない
こうした情報不足な発信は下記のような失敗につながる恐れがあります。
①ユーザーの行動につながらない
投稿を見て「なるほど」と思っても、
どうやって実践したらいいのかわからないと行動に移せません。
② 投稿の信頼性が落ちる
必要な情報が抜けている投稿は、
ユーザーに不信感を与えてしまうことがあります。
③ 途中の投稿が保存・シェアされない
投稿は「有益、見返す=保存される」「共感=シェアされる」で
拡散していきます。
必要な情報が抜けていると、保存やシェアの機会を逃してしまいます。
▶︎ユーザーにとって「必要な情報」とは?
必要な情報とは、読み手の【行動・理解・共感】を獲得する
要素のことです。
以下の視点でチェックしてみましょう。
✅「行動」に必要な情報
- 商品価格
- 申込方法(リンク・DM・LINE)
- 日程・時間・場所・期間
- 限定条件・対象者など
✅「理解」に必要な情報
- 結論(最初に記入)
- 用語の意味や背景の説明
- Before / Afterや事例
- 数値・根拠・実績の示唆
✅「共感」に必要な情報
- 背景・ストーリー
- 発信者の体験談や想い
- ユーザーに寄り添った一言
伝えるべき情報をきちんと整理し、
相手の目線で考えて書くことが縦横になります。
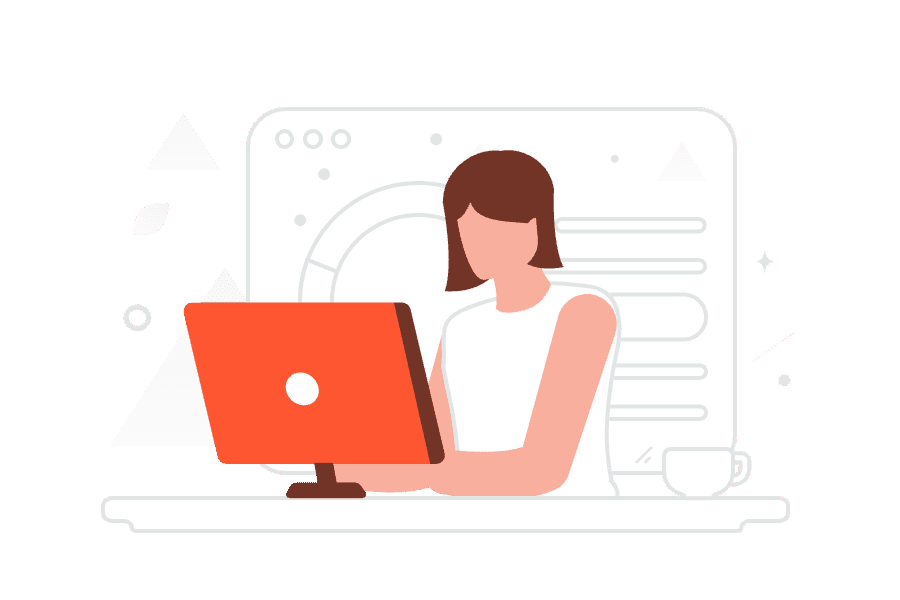
失敗例④投稿数が多いハッシュタグ(ビッグワードタグ)しか付けていない
ハッシュタグをつける際に、
ビッグワードタグをつけるのは重要なポイントです。
しかし投稿件数の多いビッグワードは、
検索される際に他の投稿に埋もれてしまう可能性があります。
また、ビッグワードは広すぎるため
届けたい層まで届かない可能性があります。
(例)
#副業 → サラリーマン、主婦、学生、フリーランス
誰に向けた副業かわからない
#かわいい → コスメ、洋服、ネイル、雑貨
対象が広すぎる
そのためハッシュタグは、
以下のボリュームのものをバランスよくつけるようにしてみましょう。
- 10万件以上のビッグワード
→認知拡大を狙って1〜2個程度使用
- 1~10万件のミドルワード
→ 内容投稿に合った、ややニッチなキーワード
→ 検索されやすく、表示される時間も長め
- 1万件以下のスモールワード
→超ニッチなターゲット層に届く
→上位表示されやすく、保存にもつながりやすい
上記の3つからハッシュタグを3~5個選び、設定しましょう。
失敗例⑤途中から投稿のテイストが変わっている
インスタ運用でよくある失敗例が、
投稿のテイストを途中からガラッと変えてしまうことです。
途中で方向性を見直し、
思い切って投稿内容を変更するケースはよくあります。
しかし、アカウントの統一感が失われてしまい、
ユーザーにとっては違和感を覚える場合があります。
たとえば、
- 商品やサービスと関連性がない投稿をする
- 色、イラスト、写真のテイストを変える
- 口調が変わる
今までにしてこなかった方法で投稿をしてしまうと、
逆に悪目立ちしてしまい、世界観が崩れてしまいます。
途中で投稿内容を変える場合は、
過去の投稿はアーカイブするなどの対策をすると
違和感なく新しいテイストを受け入れてもらいやすいです。
いかがでしたでしょうか?
今回はインスタグラム運用初心者がやってしまいがちな失敗例と
その対策について解説しました。
失敗例を見て恐れるのではなく、
まずは発信してみることが重要です。
コツコツと投稿を続ければ、
ユーザーに求められている内容を理解でき、
おのずとフォロワーも伸びてきます。
失敗から改善点を学びつつ、
ユーザーにとって有益な情報を発信していきましょう!